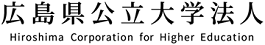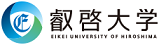本文
林 優子(はやし ゆうこ)
研究者紹介

所属:保健福祉学部保健福祉学科作業療法学コース 職位:教授 学位:医学博士
研究室:県立広島大学三原キャンパス2502号室
E-mail:yhayasi@(@の後に
研究内容:https://researchmap.jp/yhayasi
研究に関する自己PR
私は、附属診療センター発達支援専門外来で小児科医として診療を行っています。年間の初診患者は約150名、再診患者は約650名で、そのうち45%が自閉スペクトラム症(ASD)、25%が注意欠如多動症(ADHD)、10%が発達性学習症(SLD)である。診療は、正確なアセスメントから始まります。診断名や表面上の課題のみに注目するのではなく、子どもの発達特性、発達経過、環境要因などを総合的に判断します。神経発達症の支援の目標は、子どもが将来も自己肯定感をもって豊かな社会生活を送ることです。そのためには、医療?保健?教育?福祉関係者が共通理解をもって協働していく必要があります。保健福祉学部内の子育て支援部会や三原市との研究協力により、多職種連携?多機関協働システムの構築を進めています。
研究テーマ
肯定的な自己認知と行動統制をターゲットとした神経発達症の支援
?発達性学習症(SLD)の要因別支援
?注意欠如多動症(ADHD)に対する薬物の選択
?不登校児の支援と長期予後
研究の特徴?内容
?発達性学習症(SLD)の要因別支援
SLDの要因別の支援の有用性を検討する。初診患者で、SLDと診断されるのは、10%に過ぎないが、実際には、学校適応が難しい場合、学習に対する負担感がある場合も少なくない。SLDの可能性も視野に入れて、積極的に読み書きスクリーニングを行っている。『WISC-Ⅳ』、『標準読み書きスクリーニング検査改訂版(STRAW-R)』、『KABC-Ⅱ』という標準的な評価に加えて、『感覚プロファイル』『JPAN感覚処理?行為機能検査』『近視?遠視数字視写検査』『SM社会生活検査』を実施している。その結果から、SLDを広義に捉えて、(1)読むことが苦手な子どもは書くことも苦手(読み書き障害)、(2)読めても書くことが苦手(書き障害)、(3)個別ではできるが集団での学習が苦手(集団学習が苦手)の3パターンに分類し、その要因を分析している。要因がはっきりすることで、言語療法や作業療法のリハビリテーションによる発達支援、特別支援教育による環境整備など、要因に合った支援が明確になる。
?注意欠如多動症(ADHD)に対する薬物療法の選択
肯定的な自己認知と行動統制のために生活な中でどこの部分から優先的に治療するかを明確にして薬剤選択を行いその有効性を検討する。ADHDの受診目的は、就学先の検討と学校や幼稚園?保育園における集団生活の難しさ(指示通りにできない?離席?トラブル)に分けられる。作業療法や療育施設を紹介して心理社会的治療を優先しているが、社会生活上困難を伴う場合や自己肯定感の低下が進んでいる場合は薬物療法も実施し、約4分の1が対象となる。ADHD治療薬として、メチルフェニデート(MPH),アトモキセチン( ATX), グアンファシン(GXR)の3種類が保険適応である。それらの薬物の効果判定は、保護者や教員の観察による多動?不注意の程度(ADHD-RS)や子どもの家庭や学校生活の状態を捉えたチェックリスト(QCD)により主観的な評価しか行われていない。ADHD治療薬の本質的な目的は、多動や不注意の症状が強いことで認知や遂行能力が妨げられ、学習やソーシャルスキルの獲得が定型発達の子どもに比べて遅れ、そのためにおこる不利益を改善することにある。
?不登校児の支援と長期予後
学齢期における不適応症状として、不登校状態を示した子どもの特性と支援後の長期予後を分析し、今後の支援のあり方を検討する。対象は20歳となったケースのうち、学齢期に不登校状態があったケースの20歳時点の社会参加状況と本人の主観的満足度について、年金診断書および聞き取りから明らかにする。学齢期の不登校の状況や実施された各種検査結果を調査する。長期予後とそれらの関係性を統計および質的研究手法で検討する。2020年日本小児神経学会において、『発達外来における中学不登校生徒の予後の検討』として、中学時に1年以上長期に全く登校できなかったケースの高等学校での適応状況について発表した。同年齢の受診者の15%に相当する25名のうち、20名が高校(10名が通信制高校、6名が定時制高校)には適応して登校できていた。これら高校に所属していない5名も何らかの医療?福祉との繋がりがあり社会参加はできていた。生活困難度尺度は、すべて4以下で、平均値は、通信制で3.6、定時制で3.0、全日制2.7、高校在籍なしは4であった。将来を視野に入れたアセスメントと適切な社会参加の経験が重要であると結論づけた。
受験を検討している方々へ
主な実践?教育活動
(1)県立広島大学保健福祉学部附属診療センター発達外来での診療(年間実人数800名)
診療内容;発達相談、診断、治療?リハビリテーション、カンファレンス、ケース支援会議
(2)県立広島大学保健福祉学部地域連携センター子育て支援部会による保護者支援の研究
(3)三原市地域自立支援協議会児童支援部会専門委員市内の児童発達支援事業?放課後等デイサービスへの専門支援
(4)三原市就学指導委員会委員
(5)三原市保健福祉課発達相談
(6)広島県小児科医会子どもの心委員会委員
(7)広島県発達障害研究会幹事
(8)日本知的障害者福祉協会人材育成専門委員
(9)シティカレッジ、教員免許状更新講習、就学説明会などの講習会の企画?開催?講師
連携協力を検討している方々へ
(1)地域において親子のニーズを早期に把握し適切な支援に繋ぐ連携体制の拡充
(2)親子が安心して気楽に相談できる相談機能(子育て中の家族が孤立しないように)の充実
(3)専門的な診断や支援が必要な子どもが適切な発達支援を受け、途切れることなく安心して成長するための地域の専門機関の連携体制の強化
(4)基盤の脆弱な家庭に対する地域資源の充実と支援者に対するスーパーバイズ
(5)発達支援に関わる多職種が共有できる評価?支援の開発
論文リスト
著書
専門資格
小児科専門医 小児神経専門医 子どものこころ専門医 小児精神神経学会認定医
日本小児科医会子どものこころ相談医 身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師
キーワード
神経発達症 小児神経学 小児リハビリテーション 療育 多機関協働 多職種連携 保護者支援 薬物療法 肥満 生命倫理
関連情報
日本知的障害福祉協会人材育成?研修委員会専門委員:http://www.aigo.or.jp/
広島県地域保健対策協議会発達障害医療支援体制検討特別委員会委員:http://citaikyo.jp/
広島県小児科医会子どもの心委員会委員:http://www.hiroshima-ped.com/
三原市発達障害者支援検討委員会委員長
三原市就学指導委員会委員会委員長
 大学概要
大学概要
 学部?大学院?専攻科
学部?大学院?専攻科
 学生生活?就職支援
学生生活?就職支援
 研究?地域連携?国際交流
研究?地域連携?国際交流
 入試情報
入試情報